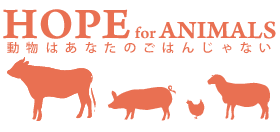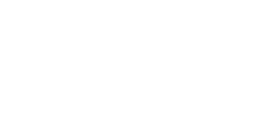世界の大豆の74%が工場畜産の中に閉じ込められた鶏たちの餌になっている。その大豆は多くが南米からやってくるようになった。以前はアメリカなどからも来ていたが、主要生産国としては現在はブラジルだ。中国もブラジルから輸入し、大豆ミールにしてから日本に輸出するケースも有る。
マットグロッソ州の農薬緩和とアマゾン大豆モラトリアムの危機 ―
ブラジルを中心とする南米の大豆(ソイ)生産は、世界の食料・飼料市場を支える巨大な輸出産業である。しかし、その成長の裏側では、環境破壊の再加速・住民の健康被害・気候変動の悪化という深刻なリスクが顕在化してきている。特に、マットグロッソ州での農薬散布に関する規制緩和、そしてアマゾン域における大豆モラトリアム(森林伐採後の土地で生産された大豆を買わないという業界合意)の変質・停止が、強く警鐘を鳴らしている。
マットグロッソ州:農薬の「緩衝距離」緩和が住民健康を直撃
ブラジル最大の大豆生産州であるマットグロッソ州では、2024~25年にかけて、農薬散布時の緩衝距離(バッファーゾーン)を大幅に縮小、あるいは撤廃する法案 PL 1833/2023が議論・可決されている。
国際人権団体 Human Rights Watch(HRW)は以下のように警鐘を鳴らした。しかし、2025年3月に可決されたようだ。
「州議会は、かつて300 mを義務付けていた住居・水源などからの地上農薬適用の距離を、大規模農場で90 m、中規模で25 m、小規模農場ではバッファーを完全撤廃するという法案 1833/2023 を審議中である」 ヒューマン・ライツ・ウォッチ
また、同州では「2009年の州令」で都市・村落・飲料水貯水池から最低300 m、泉から200 m、他の水域・離れた住居から150 mという緩衝距離が設定されていたが、法案可決によりその距離が大幅に縮められたと報道されている。
この緩和に対して、科学者・医療関係者・環境NGOからは強い警戒の声が上がっている。例えば、研究者フェランテ氏は、「バッファー距離を無くした地域で、250 m以上にわたって生物消滅・変異・異常が観測された」と述べている。
残念なことに、2025年3月に議会を通過し、4月25日に交付された。
健康・環境リスクの側面
- 農薬の飛散・漂流・流入による住民・先住民・水域生態系への曝露リスクが増大する。 HRWによれば、マットグロッソ州では農薬中毒と報告されている数件に対して、未報告のものが実際には26倍存在する可能性も指摘されている。
- 農薬使用量もブラジル国内で突出しており、マットグロッソ州だけで全国の約4分の1の農薬が消費されているというデータも存在する。
- 農業の利便性向上を目的とした規制緩和が、住民の「健康権」や「環境保護」をないがしろにする恐れがある。 HRWは「法案は農薬使用を今以上に近接して可能にし、公衆衛生と環境保護を大きく後退させるものである」と警告している。
こうした状況は、単に農薬リスクの悪化というだけでなく、森林の新規開墾・大豆畑への転用がより迅速に進む下地を作るものである。つまり、農薬・大規模化・作付け拡大という流れが連鎖して、環境破壊が加速しかねないという意味である。
アマゾン・モラトリアムの終わり:20 年続いた歯止めが揺らぐ
もう一つの重大な転換点が、2006年に導入された「アマゾン大豆モラトリアム(Soy Moratorium)」の姿勢変化・停止問題である。
このモラトリアムは、アマゾンの森林伐採を背景とした大豆生産拡大に歯止めをかけるため、国際的な買い手・大豆業界・NGOが2008年以降に伐採された土地からの大豆を購入しないという合意として機能してきた。
だが、国家競争監督機関 CADE(ブラジル競争庁)が、モラトリアムを“カルテル的”合意として審査し、2025年8月にモラトリアム停止を命じたという。 *1 *2 *3
また、州レベル(マットグロッソ州)では、モラトリアムへの参加会社に対する税優遇を廃止する州法が可決され、「モラトリアムに参加しない農家・貿易会社を優遇する」制度改変が行われた。 *1 *2
このような制度変化が意味するのは、モラトリアムという最も有効だった自律的森林保護の枠組みが弱まり、アマゾン地域で再び大豆による森林伐採が増加する可能性である。例えば、モラトリアム導入前には大豆拡大の30 %が森林伐採と直結していたが、導入後にはそれが1 %にまで低下したという。*1 *2
気候変動・生物多様性へのインパクト
- 森林は巨大な炭素吸収源であり、その大規模な伐採・転換は気候変動を一層加速させるだろう。
- 先住民・移住農民・伝統共同体の土地・生計を脅かす構図が再び強まるだろう。
- 国際市場において「森林破壊フリー」「サステナブル大豆」への要求が高まっている中で、モラトリアム弱体化は日本・欧州・中国など輸入国にとってもサプライチェーン上のリスクを意味する。
大豆拡大がもたらす「二重のリスク」
両者(農薬緩和とモラトリアムの弱体化)が示すのは、南米大豆生産における環境破壊・健康被害という二重のリスクだ。
- 環境破壊の観点:森林の喪失、生物多様性の消滅、水循環の変化、土地利用転換による生態系の脆弱化。
- 健康・社会的影響の観点:農薬曝露によるがん・神経疾患・胎児発育異常・流産などの報告、住民・先住民・農場労働者の生活・生計の不安定化。例えば、HRWではマットグロッソ州の住民が「すでに農薬による健康被害を受けており、緩衝地帯を縮めることでその危険性がさらに高まる」と報告している。
この背景には、世界的な飼料用大豆ミール(大豆粕)需要の増大(例えば日本・中国向け飼料原料として)と、それに応じたラテンアメリカ・ブラジルでの大規模化・拡張の構図がある。
アマゾンもマットグロッソ州はいわば「世界の飼料供給地」であるが、その供給網には見えづらい。日本も多くの商社、飼料輸入企業が関わりを持つ地域だ。だが、それらの企業のサイトを見ても、どこの農場から、どのくらいの飼料を輸入したかはわからない。当然ながら、卵や肉という畜産物に形を変えたときにはまったくわからず、言及すらされていない。だが、間違いなく、日本にいる鶏や豚は、これらの地域から得た飼料を使っているのだ。ブラジルからの輸入、中国を経由した輸入があるのだから・・・
農薬の規制緩和も、モラトリアムの終焉も、単なる地域的な政策変更ではない。地球規模の気候・環境・人権がかかった転換点だ。濃厚飼料のほとんど(88%程度)を輸入に頼る日本もそれに加担している。
私達は食料システムを変えなくてはならない。動物性たんぱく質から、植物性たんぱく質に変え、どこかの段階にトレーサビリティができない素材が含まれるものからは手を引かなくてはならない。