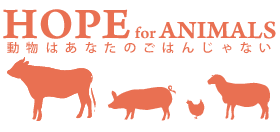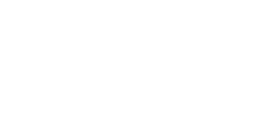妊娠ストール廃止に続く、新たなステージ
スターゼンは以前から、母豚を妊娠期間中に動けない金属ストールに閉じ込める「妊娠ストール」の使用を段階的に廃止する方針を公表しており、食肉企業としても国内で、アニマルウェルフェアに正面から取り組んできた企業の一つです。
さらに2025年に公表されたスターゼン株式会社の『統合報告書2025』においては、同社が「ケージフリー」への取り組み方針を明らかにしました。これは食肉企業としては画期的な言及であり、ホテルを中心に日本のケージフリーがグローバル化する本年に、この取り組みが明らかにされたことは、国内のアニマルウェルフェア進展に大きな影響を与えるでしょう。
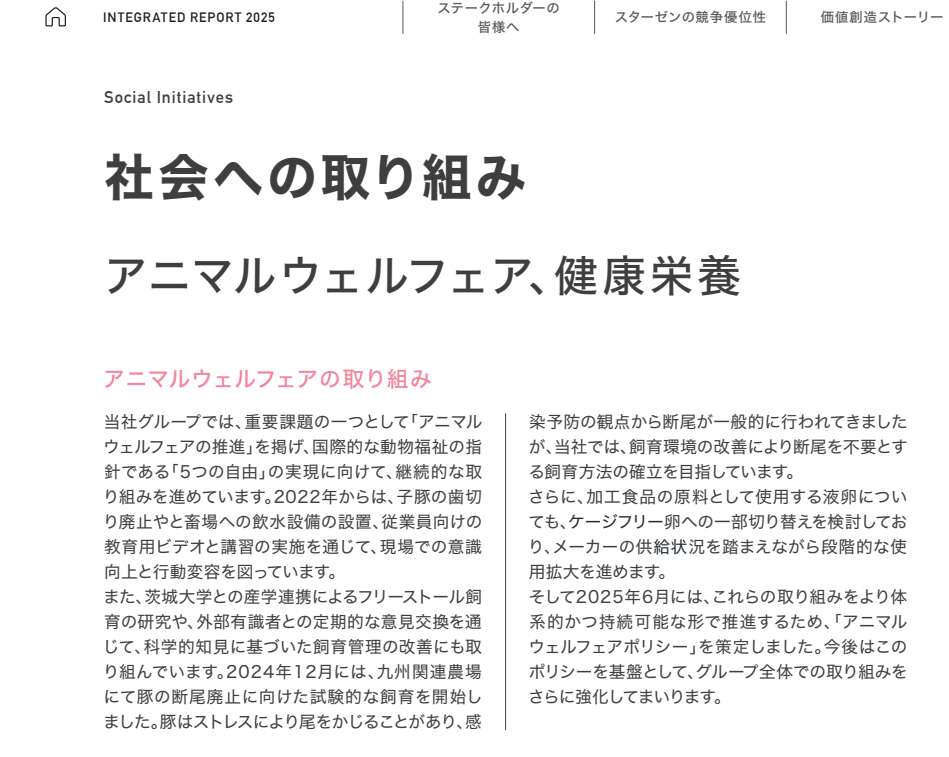
これは、同社がアニマルウェルフェアを単に法令遵守やCSRを超えて、サプライチェーン全体の倫理性と持続可能性を意識した姿勢をしめすものといえます。食肉業界の大手企業が、「卵(採卵鶏)」に関するケージフリー方針を公表したことについて、アニマルライツセンターは画期的な一歩と評価します。
アニマルライツセンター代表理事岡田千尋は「世界のあらゆる分野の食品関連企業は、卵のケージフリーに向けた取り組みを公表しており、それは食肉企業も同じです。利用するすべての畜産物のアニマルウェルフェアについて真剣に捉え、卵についても取り組みを公表しケージフリーに向けた課題解決の道をともに進むことを決断してくださったスターゼンに感謝するとともに、その姿勢を高く評価します。他の食品関連企業、食肉企業も、この前向きで良い取り組みに続いてほしいと願っています。」と評価しています。
食肉企業が「ケージフリー」を語る意義
ところで消費者には、食肉加工業と卵の関係がイメージしにくいかもしれません。ハム・ソーセージの製造販売で国民的に馴染みのあるスターゼン社は、加工食品の一部に「液卵」を使用しています。液卵とは加工目的で殻を割り、攪拌した液状卵のことで、全卵のほか、黄身だけ、加糖製品の形状で流通しています。多くの食品加工において、液卵は食品に卵の味をつけるものではなく、食材を膨らませたり、凝固させる目的で使われる原材料です。じつは世界に類を見ないほど、日本の食品工業にはこの液卵が欠かせない存在です。国内に流通する卵の約半数が加工品に使われている実態があります。一例にすぎませんが、練り物、焼き菓子、麺類など、あらゆる日本の食品には液卵が使われているのです。これまでの液卵製造においては、スーパーに並ぶパック卵に適さない規格外品を液卵加工するのが通常でした。つまり、殻付きで流通する平飼い卵の数が安定しないと、平飼いの液卵製造がうまく回らない構造で、逆に言うと、液卵の需要が目に見え始めると、平飼い全体の生産が刺激されるという大事な要素となります。
これまでケージフリー(採卵鶏をケージに閉じ込めない飼養方式)への取り組みは、主に卵や外食・小売業界が主導してきました。しかしスターゼンは、食肉企業でありながら、卵という“他畜種”の福祉問題に踏み込み、アニマルウェルフェア全体を総合的に俯瞰する企業倫理を打ち出したのです。これは食肉企業の枠を超え、たとえ少量でも卵を扱う食品企業としての在り方を示したもので、包括的に取り組まなければ、アニマルウェルフェアもサステナビリティも好循環を起こすことができないというきわめて本質的な視点をスターゼンは示しています。
畜産の現場では、豚・鶏・牛といった畜種ごとに飼養形態や課題が分断されがちですが、動物福祉の理念は本来、種を超えて共通しています。
動物たちの苦しみを軽減し、自然な行動を可能にする環境を整えることは、どの産業動物にも当てはまる原則であり、サステナビリティの根幹でもあります。
この姿勢は、食肉業界にとっても、サステナブル経営全体にとっても示唆的です。アニマルウェルフェアを一部のCSRテーマにとどめず、調達・生産・販売・消費といったサプライチェーン全体に横断的に組み込むことで、初めて持続可能な好循環が生まれる。スターゼン社のケージフリーの取り組み公開は、その連鎖の第一歩として位置づけられるでしょう。